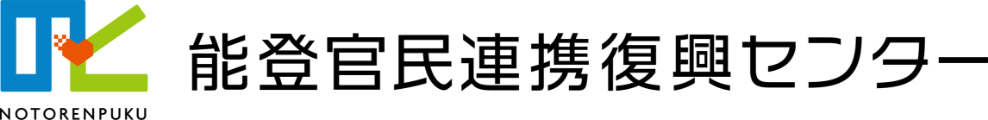お知らせ
ぼうさいこくたい2025 in 新潟に参加します
ぼうさいこくたいとは
「ぼうさいこくたい(防災推進国民大会)」は、防災・減災や災害復興に関わる全国の自治体、企業、団体、市民が一堂に会し、知識や経験を共有する年に一度の全国フォーラムです。内閣府が主催し、毎年各地で開催されています。防災の先進事例や最新の研究成果、復興支援の現場からの報告などが集まり、来場者は展示やセッション、ワークショップを通じて多角的に学ぶことができます。
特徴は、行政・企業・NPO・市民など、多様な立場の人々が立場を超えて交流できること。防災訓練や体験型企画も多く、防災の知識を専門家だけでなく一般の方にも広く伝える場になっています。
2025年は新潟市の朱鷺メッセを会場に、9月6日(土)と7日(日)の2日間開催されます。全国各地から出展や登壇があり、能登官民連携復興センターもブース出展やセッション登壇を通して参加します。
① ブース出展:「能登と全国を官民連携でつなぐ『のとれんぷく』の取組み」
本ブースの目的は、能登を「遠い被災地」ではなく「訪れ、学び、共に考える場所」として感じてもらうことです。能登に実際に足を運ぶことは、防災を学ぶきっかけとなると同時に、現地で見聞きした状況を発信いただくことが、能登の支援へとつながります。来場された皆様に、その意義をお伝えしていきたいと考えています。
私たちは、1F展示ホールA・B-022にて「能登で防災を学ぶ、能登の復興を知る」をテーマにブースを出展します。令和6年能登半島地震や奥能登豪雨からの復旧・復興の現場を通じて、「当事者として学び・関わる」きっかけを提供します。
ブースでは、石川県や各市町、民間団体が発行したチラシ・パンフレットを配布します。その中でも、震災を学べる場所やモデルコースをまとめた「能登復興の旅 プログラム集」をぜひ手に取ってご覧いただきたいと思っています。また、被災前後の写真などの紹介を通じて、災害の現実とそこからの歩みを体感できます。
さらに、センターの体制や役割を紹介し、(公社)経済同友会、サントリー、タイミー、LINEヤフーなどの団体・企業との連携事例や、休眠預金・著名人による寄附を契機として石川県が創設した「能登復興応援基金」を活用した伴走型事業など、官民が連携して進める復興モデルをご紹介します。これらは全国の自治体や企業にとっても参考となる具体的な事例です。
能登の復興を知り、防災・減災の力を全国で高める一助となる場に、ぜひお立ち寄りください。
詳細:https://bosai-kokutai.jp/2025/b-022/
② セッション登壇:「大学が担う能登の創造的復興と未来」
9月6日(土)16:30〜18:00、ぼうさいこくたい2025内で行われる金沢大学のセッションに、能登官民連携復興センター長の藤沢烈が登壇します。テーマは「大学が果たすべき役割と使命」。令和6年能登半島地震・奥能登豪雨からの創造的復興に向け、産官学それぞれの立場から議論します。
金沢大学は2024年1月に「能登里山里海未来創造センター」を設立し、オール金沢大学体制で復興に取り組んでいます。2025年度からは「防災・復興人材特別プログラム」も始動し、10年先を見据えた高度人材育成や実証研究を進めています。
セッションでは、大学の持つ知的資源や研究力を活かした支援の可能性、地元出身者としての視点、そして企業や行政との協働の形が語られます。藤沢は、現場の課題と全国的なネットワークをつなぐ立場から、大学との連携がどのように能登の未来を形づくるかを提案します。
災害復興は短期的な復旧にとどまらず、次世代のまちづくりや人づくりまで視野に入れる必要があります。このセッションは、大学がその先導役として果たせる役割を、多角的に探る機会です。
登壇者
- 谷内江 昭宏 ヤチエ アキヒロ
- 金沢大学理事・副学長、能登里山里海未来創造センター長
- 輪島市深見町出身。輪島高校から金沢大学医学部に進学し、金沢大学小児科教授、附属病院副病院長を歴任。専門は小児科学、免疫学。
- 藤沢 烈 フジサワ レツ
- 一般社団法人 能登官民連携復興センター長、一般社団法人 RCF代表理事
- 一般社団法人RCF代表理事であり、県能登半島地震復旧・復興アドバイザリーボード委員や復興庁復興推進委員などを務める復興の専門家。
- 橋口 翔 ハシグチ ショウ
- LINEヤフー株式会社 ソーシャルアクション推進室
- 2012年NHN Japan株式会社(現LINEヤフー株式会社)入社。官公庁や自治体に自社サービスの活用支援を行う。現在は防災や行政DXなど、公共分野の取り組みに携わっている。
詳細:https://bosai-kokutai.jp/2025/s-49/
③ セッション登壇:「災害からの『連携復興』を考えるラウンドテーブル」
9月7日(日)12:30〜14:00、朱鷺メッセの1F 展示控室3で行われるセッション「災害からの『連携復興』を考えるラウンドテーブル」に、能登官民連携復興センターの杉本拓哉が登壇します。本企画は定員25名の事前申込制で、参加費は無料です。
「連携復興」とは、東日本大震災後に岩手・宮城・福島で生まれた、地域と全国の多様な担い手が資源を持ち寄り、協働して進める復興の形です。今回のセッションでは、東北での経験をもとに、その考え方やモデルを能登や他の被災地にどう応用できるかを議論します。
登壇者には、災害復興に携わる研究者、自治体職員、NPO関係者など、多様な立場の専門家が集結。能登の復興現場を知る杉本からは、現地での広域連携の実践例や課題、今後の展望が語られます。ラウンドテーブル形式のため、参加者も議論に加わり、自らの地域に生かせる知見を持ち帰ることができます。
災害は地域ごとに状況も資源も異なります。しかし、経験やネットワークを共有することで、より迅速で持続的な復興が可能になります。この場は、そのための知恵とつながりを生み出す貴重な機会です。
参加を希望される方は、下記の申し込みフォームよりお申し込みください。
申し込みフォーム: https://forms.gle/qMxzLsc5w3dsg79p7
◆スピーカー
- 瀬川加織(特定非営利活動法人いわて連携復興センター 地域コーディネーター)
- 杉本拓哉(石川県能登半島地震復旧・復興推進部 創造的復興推進課現地対策室 課長補佐・一般社団法人能登官民連携復興センター 広域連携チーム マネージャー)
- 菅野 拓 (大阪公立大学大学院文学研究科 准教授)
- 田村太郎(復興庁 復興推進参与・一般財団法人ダイバーシティ研究所 代表理事)
- 澤田雅浩(兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科 准教授)
◆ファシリテーター:
- 葛巻 徹 (一般社団法人みちのく復興・地域デザインセンター)
◆進行・報告:
- 石塚直樹(一般社団法人みちのく復興・地域デザインセンター)
詳細:https://bosai-kokutai.jp/2025/w-13/
みなさまのご参加をお待ちしております。